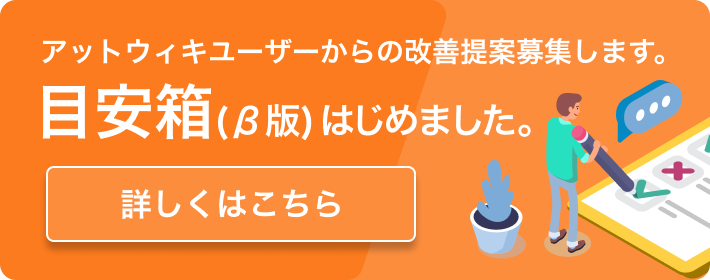アマネオ
花奥恵の青い闇(1994年)
最終更新:
amaneo
名呑町地下。
床に蝋燭が置かれた。その横肌は皮膚を焼かれた白蛇の腹のように爛れている。花奥恵の顔は蝋燭の灯に照らされ、ゆらめく橙色に染まっていた。
「私は深海魚でした」
彼女は闇の奥へ語りかける。かたわらの石造りの壁には全面に奇怪な触手が彫り込まれている。
「青闇の中に眠っていたのですが、目の前を不思議な生物が横切っていきました」
膝をつき、操られるように淡々と口を動かす。目は薄く開き、どこを見ているかも定かでない。
「それは美しい者だったようですが、今では思い出せません」
霧が彼女の周囲を包み、輪郭がぼやけて亡霊のようだ。彼女は立ち上がり、朗々と呪詞を叫んで肢体をくねらせる。
――いあ! いあ! しゅめっしゅ しゅめっしゅ しゅぶ・にぐらす・つがー!
彼女は四つ這いにひざまずき、床に接吻すると突如上体を跳ね上げ反り返った。全身を硬直させて釣り上げられた魚のように痙攣しながら叫ぶ。
――ぺるくら ぺるまぎ ばふゅそわ えす えすけさ らん えまのん・つがー! つがー! いあ! いあ!
やがて彼女は弛緩し、朦朧とした意識で再び語り出した。
「――その時、私は釣り上げられました。私は汚れた地上へ昇っていきます。水圧が変化し、私の皮膚は沸騰したように綻び、浮袋が喉から飛び出て真っ白な世界へ――そこで目を覚ましたのです」彼女は気を失い、ふぬけのような顔で白目をむいて倒れた。
花奥恵の様子がおかしくなったのは(まァもともとある程度はおかしかったんだが)、まだこの町にリリジョン101の影が薄かった頃だった。だから一心不乱に何か作り始め、
「マハカメリア宮に頼まれて」
なんて花奥が言ったときでさえ、俺は何かまたおかしな設定をこしらえやがったな、くらいにしか考えてなかった。多分一生モンの後悔だ。
ことあるごとに花奥が呟いたのは「見えないつながり」という言葉だった。俺の大嫌いな言葉。
「その、どうしてそういう絵を描こうと思うんだ?」
ある日の俺は花奥に聞く。
「どうかな。わかんないけど、どこか遠い誰かが、何か面白いことをやったり、ぼそっと呟いたりしてるの」
花奥は一切こちらを見ない。
「私はそれを見に行きたい。聞きに行きたくてたまらない。見えないつながりがそこには確かにあって。でも遠くて、どこまでいっても追いつけないから、仕方なく私は私でそれってこういうものかなって感じで作品にする」
花奥は笑って、わかんないだろうな、と続けた。
わからん。
俺には「見えないつながり」が見えない。だって見えないんだから。ただ、花奥は「見えないつながり」こそが大事だと言っていた。花奥に、マハカメリア宮について尋ねたが要領を得なかった。
分かったのは、マハカメリア宮はその「見えないつながり」を束ねて持っていて、そいつの所には面白いことがたくさん起こるから花奥は好きらしいことだ。
像を作るときの花奥は嵐のように凄まじかった。
「見えないつながりは夢の青闇の中にあるんだ」と言って聞かず、寝て起きては「あの夢の続きを」と言ってまた寝るということを二週間ほど繰り返して衰弱死しかけた。
それで何かをつかんだ花奥は、今度は寝ずにデッサンを描きはじめた。夢の青闇にあるものをこっち側にもってくるためには、寝ながら描かなくちゃいけないと言って。
花奥はみるみる痩せ細り、即身仏のようになっていた。何も見ずカンバスに向かって微動だにせず、よだれを垂らしながら夢と現を彷徨する。
「ここ置いとくからな!」
聞こえているのかいないのか、脇にある俺の弁当はただ腐るばかりだった。授業中に窓から乗り込んできて誰彼かまわず赤ペンキをぶちまけ、その中でひゃ
ひゃひゃひゃって猿みたいに笑ったこともある。何日も洗ってない髪は脂ぎって、妙にテカテカして顔面は痩せている。落ち窪んだ目は、奥からどろり澱んだ鯰
の目じみた光を放つ。
テレビ局の取材に来た人間は、これは使えないと言って早々に帰っていった。
「天才美少女芸術家」のあっけない終焉。
我が校の歴史で最高の人物だ、なんて風に持ち上げてた校長は、花奥がそうなってしまったという悪評と責任を恐れて他言を禁じた。花奥はかなり前に親に縁を切られていたから、もう誰も止める奴はいなかった。
俺以外には。
俺は食べられることのない弁当を意地のように作り続けた。
その頃には、花奥はデッサンから造形の段階に入っていた。俺はもう殴ってでもやめさせる覚悟で美術室に行った。入った途端、息ができなくなった。
花奥に首を締められていた。
花奥は意思の汲み取れない大きな瞳で俺の表情を観察し、解放すると粘土に手を加えた。
「何なんだよ、お前! そんなにまでやる必要があるのか」
花奥は答えない。
「頼むから俺の弁当食えよ! 今日のはエビフライ入ってんだ」
花奥は近づいてくると俺を突き飛ばした。弁当が落ちて床に散らばり、もう食えない。
「飯を粗末にするな馬鹿!」
花奥を殴ったが、相手が相手だけにうまく力が入らなかった。花奥は奇声をあげながらぶつかって俺の右脚を持ち上げ、そのまま美術室から押し出した。
鼻先で扉に鍵をかけられた。俺は黙って数秒考え、言った。
「なあ、花奥。じゃあ最後だ。答えてくれよ。答えたら、もう何も言わない。勝手にしろ」
扉の向こうからは返事がないが、聞いているのはわかった。
「お前の大事な『見えないつながり』だが。それは目の前にある俺とのつながりを消すぐらい大事なのか? 見えるものをしっかり見る方が大事なんじゃないか? 俺は必要ないか? お前の中にいちゃいけないか?」
返事はない。
「答えろよ花奥恵!」
粘土をこねる音が聞こえた。俺は廊下を歩き出した。急いで帰ろうと思っているのにすぐ足が止まる。走りだしてもすぐ動けなくなる。俺は階段を一段ずつ降りながら、どうにもできずに踊り場で座り込んだ。
完成したのはその次の日だった。花奥恵は嘘のようにけろりとして、像を作り始める以前と全く同じように戻った。
像は蝙蝠とタコが合わさり、その触手が顔に巻き付いた、全身に鱗がびっしりと張り付いたものだった。どことなく名呑町に古くからあるゑびす像に雰囲気が似ていることを聞かれ、花奥は「同じテーマですから」と答えた。
世間は素晴らしい出来だと褒めちぎってるが、俺は吐き気を催す。花奥は以前と変わらないように話しかけてきたが、俺はあいつが近付くと頭痛がするようになっていた。
もう元には戻れないことを悟り、俺は高校を卒業して名呑町を出た。最後に見た海沿いの島は、それでも単純にきれいだと思った。