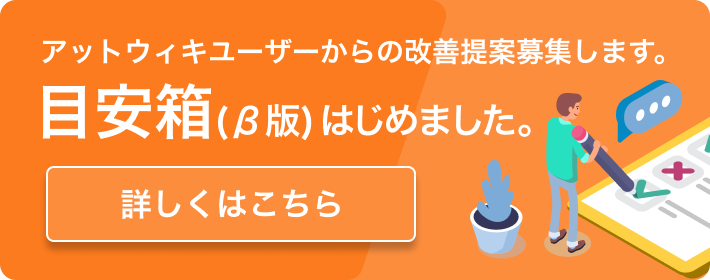アマネオ
あまねお(2013年)
最終更新:
amaneo
名呑小学校三年一組の教室では、元気いっぱいの声が響いていた。
「夏休みの日記を返しま~す。名前を呼ばれたら取りに来てね」
細身の担任教師、山際は出席番号順に名前を読み上げていく。生徒たちが一人ずつやってくる。
「瀬戸内うみねねー」
返事もなければ姿もない。
「先生、ウミネネは休み」
気がつけば教壇の傍に、目つきの鋭い褐色の少年がいた。艶やかな長い黒髪は、首の後ろで縛られていた。山際はこのどこかエキゾチックな雰囲気を携えた美少年を見るにつけ、心中で感嘆の溜息を吐いていた。
「先生?」
「あ、ああ。じゃあ――瀬戸内こかげくん」
コカゲは一瞥して、すぐに顔を背けて答える。
「うい」
「放課後、職員室に来て」
ぴく。
コカゲの左瞼が一瞬だけ痙攣した。ブツブツと「なんで僕だけ」と周囲に聞えるように独り言を撒き散らした。
「ごめんね、ちょっと君の日記のことで」
放課後の職員室にはほとんどの教師がいた。しかしコカゲに睨みつけられると誰も目を逸らした。この妙に大人びた八歳児に興味はあっても、かかわり合いになると面倒そうだと全ての教師が思っていた。
新人の山際先生を除いて。
「あまねお、って何かしら。タコやクラゲみたいに書かれてるけど」
山際は日記を繰りつつ尋ねる。
「アマネオはアマネオやけど」
「知らないなあ」
山際は腕をこまねいて、演技じみた動作で首を傾げた。傍から見ると、まるで子供向け教育番組のおねえさんのようだ。
「秘密なんやけど」
しかしコカゲは相変わらずの仏頂面だ。
「言えるだけでいいから、話してくれないかなあ。気になるなあ、気になるなあ」
コカゲは肩をすくめ、やれやれ仕方ないな、といった表情で話し出した。山際の口角がニッと上がった。
「海で見つけたけど陸にもおって、お母さんを探しとるんよ。ぶよぶよしとって変」
「ふうん」
山際は、コカゲが熱中するように身振り手振りをいれて話すのを見て嬉しくなった。いつも興味なさげでクール。そんな彼の別の面を見ることができたのだ。
「それで岩のところ――波の――食べられて――手が長くて――青色で――」
コカゲを帰し、山際は隣の特別美術教師に話しかけた。唇がぽってりと厚く官能的、常に月光の下にいるように白い肌という美貌の女性。しかし化粧は苦手らしく、眉毛の形がうまく整っていない。
「花奥先生、聞いてましたよね。あまねおって何なんですかね」
生徒の名簿をチェックしながら答えるのは、誰あろう花奥恵だった。
「こかげくんの創作でしょう。子供はみんなシュールレアリスト。ブッ飛んでるものですよ、まあ私も常にそうありたいと思うけど」
花奥は立ち上がると「じゃ、これで。明日の授業準備があるから」と職員室を出ていった。その小脇には人間の頭ほどの、タコとコウモリを混ぜたような像が抱えられている。授業用の教材だった。
どこから漏れたのか、やがてアマネオについての噂話は校内を席巻した。
曰く、あまねおは目が大きくてそこから汁を飛ばす。
曰く、あまねおは中庭の林の中にいた。
曰く、あまねおは夜、プールにいる。
曰く、あまねおはうるさい子供に逢いに来る。
曰く、あまねおは帽子をかぶっていない人を頭からボリボリかじる。
子供たちは林には近づかず、授業でもプールに入りたがらず、休み時間は不気味なほど静かになり全員が帽子をかぶった。山際は「あまねお」についての噂はデタラメである、と保護者への注意プリントを作ることを任せられた。
「馬鹿馬鹿しいですよね、ホントに」
キーボードを叩きながら花奥に愚痴る。
「え、何が」
彼女はアーティストらしく気合の入ったサイケな緑色の帽子をかぶっていた。
「もういいです」
そんなある日、山際は生徒たちが騒いでいると聞き三年一組へ駆け付けた。ドアを開けると教室の中の異様な空気に、山際の肌が粟立った。
「どうしたの」
泣き出している子や窓の外を見ている子も多いが、そこにいた全員が一様に「あまねおが来た」と言った。
問いただすが、何も語らない。
トイレから帰ってきたコカゲは、そのことを山際から告げられ黙り込む。後ろにまとめた髪を撫でながら、じっと何か考えていた。
「集団ヒステリー?」
山際はスクールカウンセラーに聞き返した。
「ええ、UFOやコックリさん、アレと症状がよく似ているんです。大人がいない休み時間の教室という限定された空間。勉強や都市伝説で子供たちには多大な
ストレスがかかっていたこと。恐怖の対象に『あまねお』という名前がつけられてしまい、想像が一致しやすくなっていたこと」
さすがに慣れているのか、ベテランの彼の話はフォークやスプーンを順に並べていくように正確だった。眼鏡の奥からの鋭い視線は、手元の本に向けられている。
「例えば、教室にゴキブリが出たとしましょう。見た子供が『うわ!』と言って逃げる。逃げる人を見たらどうしますか、誰だってとりあえず逃げるでしょう。
すると逃げる人が増える。逃げている人が沢山いることだけは『事実』です。だからそれを見た人はこう思う。原因が何かあるに違いない、噂のあまねおが現れ
たに違いない、とこうなるわけです。最初に見た子ですら『え、あまねおが出たの』と他人から聞いて思い込む」
「じゃあ、本当はやっぱりいないんですね!」
山際は身を乗り出して笑顔になった。
「ええ、そうです。というかそんなのいるわけないでしょう。くだらない小説じゃないんだから。従って、本当なら先生方にはそんな風に校内で帽子をかぶったりして一緒になって煽るのはやめてもらいたいんですがね」
山際は苦笑いして、お気に入りの麦わら帽子を取った。
しかし次の日、とうとう「あまねお」に襲われた人間が出た。花奥恵だった。美術室から職員室への渡り廊下で、巨大生物に突き飛ばされたという話だった。
「大丈夫ですか」
「平気平気。あのね、こんな奴だった。ちょうど帽子をかぶってなかったから襲われたんだけど」
花奥恵のスケッチした「あまねお」は、触手と大きな口を持つ巨大な一つ目のトカゲじみたものだった。ミノカサゴのようにヒレが幾重にも連なっている姿を描きながら、花奥はどこか嬉しそうだった。
「今ここで面白いことが起こってるって感じがするんだ」
校内放送で謎の生物「あまねお」に注意するよう呼びかけが始まった。前代未聞のことで学校側も警察に相談したが、相手にされなかった。
その数日後、アマネオの噂通り子供がプールで溺死しているのが発見された。学校側は数日間休校にして再開したが、また同じように子供が死んだ。今度は三 人だ。警察は死因を発表しなかった。プール周辺にはブルーシートが常にかけられ、立入禁止になった。子ども達はブルーシートの奥に潜む魔物を怖がり、休校 にも関わらず度胸試しで赴いた男子は泣きながら「あまねおが出た」と叫んで帰ってくるのだった。
小学校が同じように再開した日、放課後にコカゲが山際に会いに来た。
「話があるんやけど」
「何かな」
山際はしゃがんで目線を合わせる。コカゲは後ずさりながら、隣にいる花奥をちらりと見た。
「ここじゃアレやし、あっちで」
人通りのない立入禁止プールの裏で、コカゲは壁にもたれた。ブルーシートをぱたぱたと無意味にはためかせる。
「皆が言っとるあまねおは違う。陸に来ることもあるけど、あまねおはふだんは海におるもんやし帽子とかも関係ない」
「じゃあ皆がこの前見たり襲われた、アレは何だったのかしら」
コカゲは壁を二回叩き、合図する。プールから人型の化物が水面を割るように現れた。どこが目か口かもわからないこの奇怪な生物は全長ニメートルほどもあり、両腕が数十本の触手になっている。花奥の描いたものとは似ても似つかない。
「ひ」
山際は腰から崩れ落ちた。草むらにいたバッタがキチキチと鳴いて飛んでいく。
「出てき!」
コカゲが怒鳴ると、怪生物の腹が裂け裸の女の子がおずおずと出てきた。乾電池に似たアルカリ性の臭いが周囲にたちこめる。女の子は粘液まみれになっているが、色白の肌は赤ん坊のようにきめ細かい。濃い栗色の髪はべっとりとヘドロのようなもので固まっている。
似ていないがコカゲの双子の妹、ウミネネだった。
「皆が教室で見たあまねおは、コイツの仕業なんよ」
「――へ?」
山際は腰が抜けて立てなかった。
山際はコカゲから一通り説明を聞いたがチンプンカンプンだった。彼女がひとまず脳内で補足してまとめると以下になる。
コカゲが日記に書いた「あまねお」は、海へ帰って――というか水族館へ帰って――からも時々やってきた。アマネオは、通常は赤ん坊と同じ大きさで不定形だが、人間と融合する(コカゲらは「あまねおになる」と表現した)と大きな化物になれた。
ウミネネの持って生まれた資質なのか、融合するといきなり動かすことができた。練習もなしにいきなり自動車に乗れるように。コカゲも試したが、振り回されて海の底へ連れて行かれそうになったのでもう融合はする気はなかった。
生まれつき病気がちのウミネネは、そうして融合すると相性も良く思う存分動けて嬉しかった。ウミネネは新学期になっても学校には行けなかったが、コカゲからその話だけは聞いていた。
コカゲはアマネオのことをクラスメイトに話したが、皆、コカゲを嘘つきだといって信じない。
そのことを聞いたウミネネは、コカゲに無断でアマネオと融合し、昼間の学校に赴いた。噂話が加速したが、コカゲもこの時までは噂だと思っていた。ウミネネは人を驚かせるのが楽しくなり、教室へ現れた。子供たちは怯えた。
その時、コカゲはウミネネのせいだと気づいた。ウミネネは叱られ白状することにしたが、それから事件が起こりすぎて会えなかった。
「ごめんなさい」
ウミネネは目を閉じ、足を交差させてもじもじさせながら謝った。
「ちょっと待って。花奥先生を襲ったり、プールで子供を殺したのはあまねおじゃないの?」
二人は顔を見合わせて、頷きあう。
「あまねおはそんなことせんよ。もし僕らがあまねおになってそういうことするなら、爪の先まで残らんように喰うし」
そう言って双子は笑ったが、山際には何が面白いのかわからなかった。
「じゃあこれは暴行殺人事件じゃないの! 警察は何をしてるの」
山際は声を荒げて憤慨していた。双子はキョトンとした顔で見つめる。
「ある人から聞いたんやけど、名呑町ではほんとはたくさん事件が起こっとるけど警察は動かんのやって」
「どうして」
警察はプールで死亡した子ども達の死因や状況を公表していない。山際は、警察が捜査しているというように教頭から話を聞いていたが、実際に捜査しているものは見たことがなかった。
「警察はリリジョン101の味方しとるけん」
リリジョン101。名呑町を中心に広がっているカルト教団である。
「じゃあこの事件も捜査されず、迷宮入りするってこと」
「しかもあまねおのせいにされてよ。やけん真犯人を喰わないかん。このあまねおで」
既にアマネオは十分の一ほどに縮み、コカゲの脚に「お母さんお母さん」といって黄緑色の触手を絡ませる。
「殺すなんて。真犯人は、もしかしてわかってるの」
「ある人から聞いてね」
「岩本さんにさっ」
ウミネネが堪えきれない様子で言った。
「バカッ。しゃべるなって言われたろ」
「それで、誰なの犯人は」
双子は、校舎の方を同時に指差した。
山際とコカゲが夕方の廊下を歩いている。オレンジ色の光がリノリウムの緑と混ざって奇妙な雰囲気を醸し出していた。ウミネネの姿はそこにない。
「先生、悪い。ウミネネがバカで、こんなんなっちゃって」
「うみねねちゃんは、こかげくんが嘘つき呼ばわりされるのが嫌だったんじゃないかな」
山際先生が言うと、コカゲは困ったような顔で笑った。
「それでもウミネネが悪い」
二人は目的地に到着し、深呼吸してドアを開けた。美術室の中には、大量の像があった。それらは一つ一つ手作りされた、リリジョン101の本尊、タコとコウモリの混ざった像だった。その中央には、巨大な赤い花と女神のボディペイントを施した花奥恵が全裸でくつろいでいる。
醜悪な像に囲まれた黄昏の美女には、どこか神々しいものがあった。
「花奥先生、何をされてるんですか」
山際が尋ねると、花奥は笑顔になった。
「これ、生徒たち皆が作ったのよ。私の授業で」
「僕は作ってない」
コカゲが言うと、傍らの名簿を見て頷いた。
「そうね。川島くんも八木田さんも比奈さんも綾居さんも作ってなかった」
その名前は、全員プールに浮かんで死んでいた者たちだった。
「だから殺したんですか」
「殺したっていうか、マハカメリア宮に同期したっていうか。でもダメ。うるさいし、話は聞かないし、信じないんだもんね、作らないんだもん。うるさいし、話は聞かないし、信じないんだもん、作らないんだもん、うるしいし、うるさいし、うるさいし、うるさいし」
「自首して下さい」
言った瞬間、山際の脇腹をコカゲが突いた。
「先生、バカ? 自首したって警察は何もせんって」
花奥は二人がいないかのように粘土をこね始めた。
「なら、もうこんなことはやめてください」
「どうして皆、真理がわかんないんだろうね」
つぶやきながら、あっという間に粘土を猫にした。
「どうして皆、わかってくれないんだろうね」
粘土は再度こねられ人間の手になった。天才的な造形力だった。
「離れてく奴もいるしさァ。必要とする。必要としない。わかんない」
次は男の顔だった。しっかりと形を整えて表情までつけているが、山際やコカゲには誰かわからなかった。
「それじゃコカゲくん、君はわからない子だから同期しようか」
コカゲに近寄っていくが、山際がその前に立ちはだかった。
「あの、花奥先生って、そんなキャラでしたっけ。絵が好きで天才なんじゃありませんでしたっけ。ちょっと今、気分がおかしくなってるんじゃないですか」
花奥は山際の首を掴むと、ギリギリ締め上げ始めた。
コカゲは冷静に壁を二回ノックした。アマネオと融合したウミネネが、窓を突き破り入ってきた。四つ這いになったアマネオの細長い手足は、アメンボのように鋭角に折れている。白いのっぺらぼうの顔に裂けるように横線が入ると、そこから真っ暗な大口がガパンと開いた。
幾重にも並んだ歯の奥にはホース状の器官、そこから溶解液を吐いた。花奥恵の絶叫とともに、周囲に肉の焦げる臭いがたちこめた。
「ウミネネ、やれ」
一瞬にして花奥恵の全身がアマネオの口の中に消えた。
ぼりん、ごり。ちゅる。ごき。くちゅ。べき。ぽきぽき。じゅるるるるるるるルルルルゥゥ。
残ったのは山際の首にかかった両腕だけだった。
「――ゲホ、ゲホ。ごめんなさい、二人共。子供にこんなことさせて守ってもらうなんて」
「や、あいつはどうしようもなかったし」
山際は反射的にコカゲを叩いた。
「どうしようもないことなんてなかった。誰だって、何も死ぬことはないのよ。やり直しできたはずよ」
コカゲは、赤くヒリヒリと痛む頬を押さえながら「理不尽だ」と泣きそうな顔になった。
「ごめんね」ウミネネはアマネオの身体から出てくると、吐き続けた。
「大丈夫なの? ウミネネちゃんは」
「――大丈夫。アマネオを着て何か食うと、その味が着とるやつにも伝わるんよ。やけん」
冷たく、投げやりな言い方だった。
「それって全然大丈夫じゃないでしょ」
コカゲは慣れた手つきでウミネネの背中をさすってやり、身体が冷えないように自分の上着を着せた。ウミネネは双子の兄に背負われて眠った。縮んだアマネオは、その後ろをついてまわる。
山際は彼らを自分の車で送り届けた。家では、心配していた父親が二人を叱ろうとしたが、山際の言葉でなんとか済まされた。
別れ際、コカゲは山際に言った。
「ばいばい先生、また明日」
「うん、おやすみこかげくん」
コカゲは数秒考えて、言った。
「僕、先生のこと嫌いやな。うわっつらばっかりやし流されやすいけん」
「――そうね。先生も先生のこと嫌いだわ」
山際は俯き、それ以上何も言わなかった。
「でも、人のことを滅多に誉めん父さんが誉めとったよ。さっきの、ウミネネと僕が怒られんようにえらい剣幕で守ったこと」
山際は、この偉そうで素直じゃない子供が、励ましてくれているのに気付いた。自分を叩いた相手なのにも関わらず。
「そう。こかげくんは、優しいんだね」
「なんで。ほめとったのはお父さんなのに。さっさと帰りい」
コカゲは山際の背中を押して車に乗せた。
「じゃあね」
「ん」
軽自動車は夜道を照らし、まっすぐ進んで帰っていった。